©Hattrick
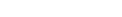
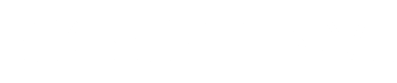

代表が海外のクラブチームと試合をするのが「代表戦」だった時代がある。世界はまだ遠いところで、ワールドカップ(W杯)や五輪の予選を除けば、世界と戦える国際試合の舞台はほんのわずか。それが往時の「キリンカップ」だった。
代表対クラブチームという変則カードは、それはそれで面白くてね。1990年代に入ると僕も出場しだし、イングランドやブラジルの名門に自分たちの技量を測れるとなれば楽しみしかなかった。国立競技場が埋まり、視聴率も上がったのは1991~1993年あたり。ただしそれよりも前、1970年代からキリンカップは脈々と開催されている。それなしには、その先、今へと連なる隆盛も起きなかった。
ヨハン・クライフ、静岡の市営グラウンドに降り立つ――。自転車で見に行ったのは中学生のころだったかな。「空飛ぶオランダ人」の真横まで近づけるくらいにセキュリティーは緩く、スターはスパイクを指さして芝生のはげたピッチを罵っていた。こんな所でサッカーできるかと、前半で交代。子どもながらせんえつにも「ちゃんとやれよ」とつぶやいたのを思い出す。
同じように憧れのリベリーノを生で目にしたときの感動は今でもありありとよみがえる。客はまばら、雨でぬかるむピッチで、勝負のさなかに「エラシコ」をさく裂。たまげた。これが1970年W杯を優勝した本物なんだ、ものが違う!
欧州のチームに観光気分が透けて見えたのは事実で、対する南米の選手たちは日銭を稼ぐことへのひたむきさをにじませていた。「サッカーはヨーロッパにとってはビジネスライクでも、南米の人には生きがいそのもの、楽しみなんだな」。一概にはいえないことだし、当時は言葉で理解したわけでないけれど、無意識ながらもうっすらと感じ取っていた気がする。
僕がゴールしてイングランドのトットナムを4-0で破った衝撃が脳裏に焼き付いていると、40代も半ばのファンが語りかけてくることがある。子どものころの驚きは色あせない。6月6日のブラジル戦も、続くキリンカップも、日本の少年のそんな一ページになり得るのだと思う。
あの日のように、名門クラブをしげく日本に呼んでくれないかな。ようこそ、鈴鹿へ。来てくれないか。